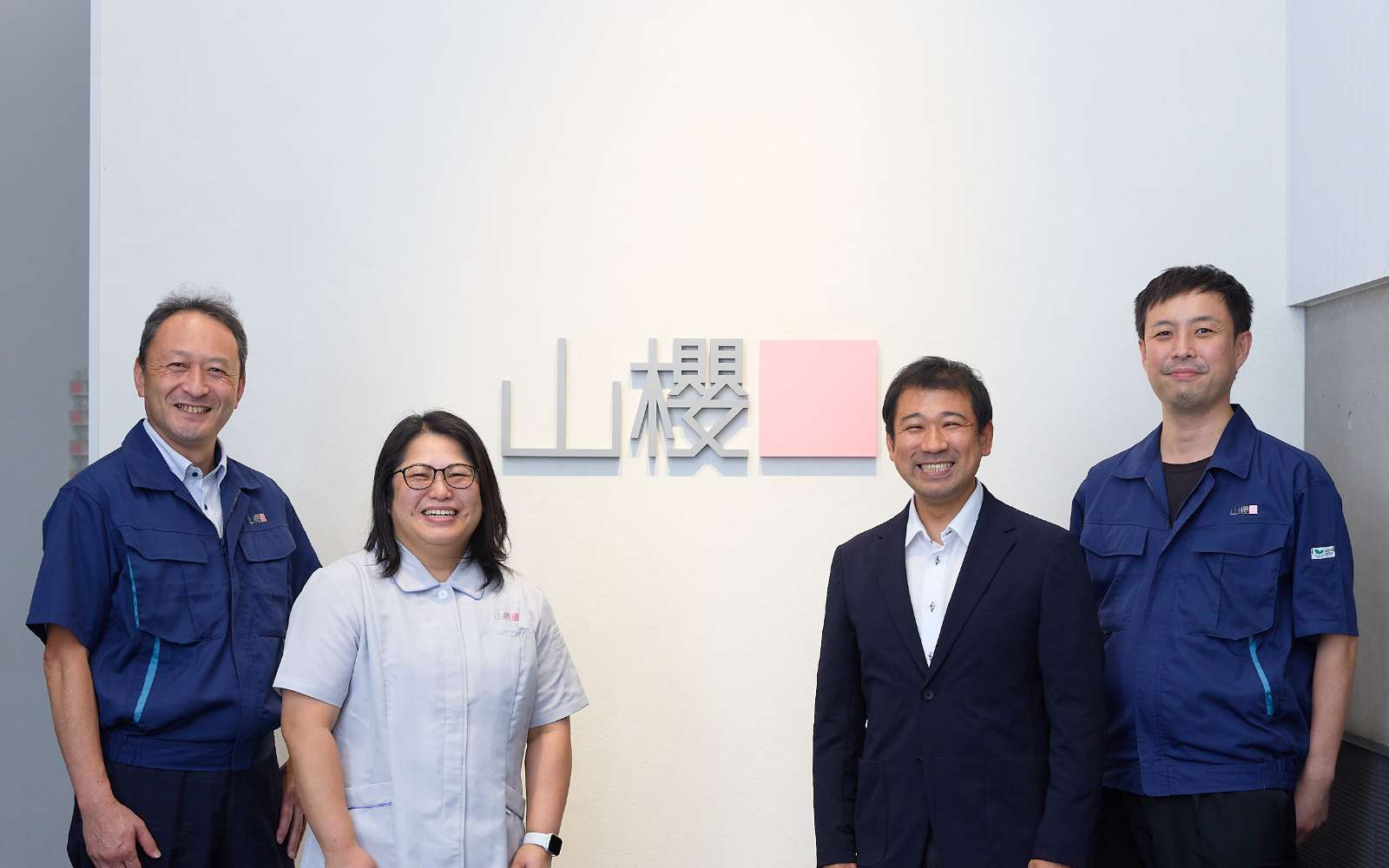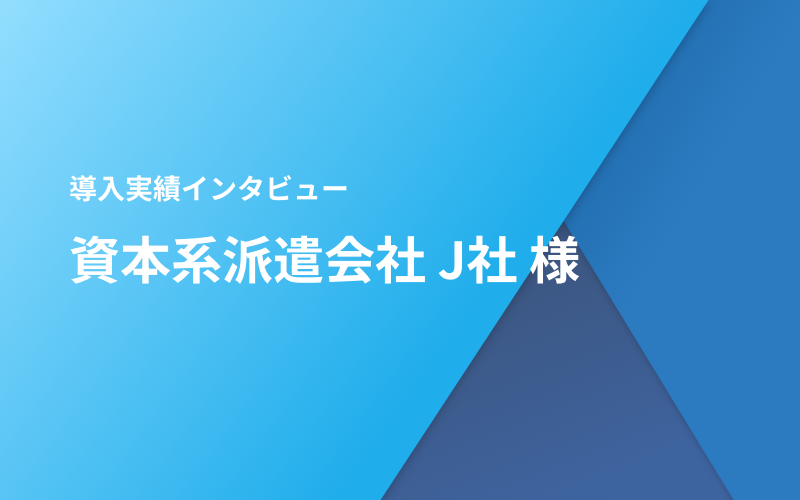株式会社山櫻 様
- 課題
-
勤怠情報の記録を保管する義務化が必要に
勤怠管理手法が本社側と工場側で異なる仕組みで管理が煩雑
タイムカード回収からデータ集計までの作業負担が大きい
- 解決策
-
DigiSheetで勤怠管理を統合、DigiFaceAIで工場メンバーの打刻を実現
勤怠情報の収集から集計まで、管理者の負担を大幅に軽減
デジタル化によって現場のDX推進に貢献
- 導入効果
-
名刺・封筒・挨拶状などオフィス用紙をはじめとした紙製品を軸に事業を展開している株式会社山櫻では、本社と工場での異なる勤怠管理の運用で管理工数が膨らむなか、統合された勤怠管理システムとして自社の運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能な勤怠業務効率化サービス「DigiSheet」および工場でのタイムカードによるアナログな運用から脱却するための顔認証出退勤打刻システム「DigiFaceAI」を導入。勤怠管理基盤を統一化することで業務の効率化を実現。
- 導入サービス
本社と工場でそれぞれ異なる手法で勤怠管理を行ってきましたが、法改正による勤怠情報の管理強化や勤怠業務の統一によって業務の効率化を図るべく、株式会社ヒューアップテクノロジーが提供する顔認証による正確な出退勤打刻が可能な「DigiFaceAI」および打刻情報を集約して出退勤管理を効率化できる「DigiSheet」を導入しています。
工場と本社での勤怠管理の運用がバラバラ、統合的な環境整備が必要に
1931年の創業以来、名刺・封筒・挨拶状などの紙製品を軸に事業を展開している株式会社山櫻。カーボンニュートラルをはじめとしたSDGsへの貢献や社会問題の解決に寄与できるよう、環境保全などに配慮したエシカルという考え方を製品やサービスに取り入れており、Webサービス事業やプリンター事業、セカンドブランドの展開など紙製品以外の分野でも事業領域を拡大しています。
同社におけるものづくりの中核となるのが、マザー工場としてジャスト・イン・タイムの生産体制の強化を進めている八王子の森工場です。製造部や技術部、管理部合わせて130名を超えるメンバーが在籍する同工場では、オンデマンドでの受注にも迅速に対応できる生産体制の強化や一貫生産して顧客に納品する機能強化を進めています。また工場内で使用する電力全てをグリーン電力に切り替えるなど、環境に配慮したモノづくりを徹底しています。
 そんな同社において課題が顕在化していたのが、勤怠管理の仕組みづくりでした。八王子の森工場をはじめ、物流部門やオフィスにある本社機能に従事するメンバーの給与計算や採用、勤怠管理含めた労務管理全般を担っている人事部門 人事室 室長 小松原 克之氏は「勤怠管理については、紙のタイムカードを中心とした工場と紙による本人申請に基づいた本社部門において異なる方法が採用されていました。アナログな運用ではタイムカードの回収から上長による確認作業、そして勤怠記録をExcelにて集計するなどの手間がそれぞれかかっていたのです」と当時を振り返ります。そこで、勤怠記録の保存が義務化されたという外的要因も相まって、デジタルツールを活用して管理負担の軽減につながる勤怠管理の仕組みを統合するDX推進へと大きく舵を切ることになったのです。
そんな同社において課題が顕在化していたのが、勤怠管理の仕組みづくりでした。八王子の森工場をはじめ、物流部門やオフィスにある本社機能に従事するメンバーの給与計算や採用、勤怠管理含めた労務管理全般を担っている人事部門 人事室 室長 小松原 克之氏は「勤怠管理については、紙のタイムカードを中心とした工場と紙による本人申請に基づいた本社部門において異なる方法が採用されていました。アナログな運用ではタイムカードの回収から上長による確認作業、そして勤怠記録をExcelにて集計するなどの手間がそれぞれかかっていたのです」と当時を振り返ります。そこで、勤怠記録の保存が義務化されたという外的要因も相まって、デジタルツールを活用して管理負担の軽減につながる勤怠管理の仕組みを統合するDX推進へと大きく舵を切ることになったのです。
柔軟なカスタマイズと多様な打刻方法が選択可能なDigiSheetに注目
新たな仕組みでは、従来のようなExcelでのデータ管理から脱却して統合管理できるソリューションを軸に、PCを貸与されている本社部門ではPCでの打刻が実施でき、工場についてはタイムカードに変わる新たな打刻方法が可能な仕組みを検討。当初は、人事システムが持つ勤怠管理の仕組みを前提に検討したものの、大企業向けで柔軟なカスタマイズに対応できないものでした。
そこで注目したのが、ヒューアップテクノロジーが提供する勤怠業務効率化サービス「DigiSheet」および顔認証出退勤打刻システム「DigiFaceAI」でした。「DigiSheetであれば、労働時間や休憩時間の考え方といった我々が考える運用に合わせて柔軟にカスタマイズできることがわかったのです。ICカードや生態認証といった打刻の仕組みも複数の手法に対応できる点も大きかった」と小松原氏。カスタマイズについても、汎用性の高い仕組みながら自分たちで個別の設定ができるなど一部内製化にもつなげていけることを評価したのです。
特に工場で行われる出退勤時の打刻に関しては、紛失や再発行、棚卸など管理の手間からICカードの運用は避けたいところで、本人が持つ顔情報をベースに打刻が実施できる点を高く評価しました。また、クラウド環境にて利用できるサービスだけに、基盤管理などの負担軽減にもつながると判断。「指紋などの手段でも良かったのですが、顔認証でテストをして見たところ、打刻スピードも申し分なく運用的には問題ないことが分かりました。工場で働くメンバーの負担にならない環境として、十分活用できると考えたのです」と小松原氏。汎用的なタブレットに備わったカメラを使うことで顔認証できる点も高く評価したポイントの1つです。
他のソリューションに比べてコストパフォーマンスが高く、提案段階から緊密にコミュニケーションが図れたこともあり、ヒューアップテクノロジーの支援体制についても十分評価しました。結果として、異なる勤怠管理運用を統合し、打刻方法の異なる環境を1つのプラットフォームに統合できる仕組みとして、勤怠業務効率化サービス「DigiSheet」および顔認証出退勤打刻システム「DigiFaceAI」が採用されたのです。

勤怠管理の統合を実現、管理負担の軽減と紙削減に大きく貢献
現在は、工場と物流拠点とともに、本社も含めて500名ほどがDigiSheetを活用しており、本社はPC上での打刻を、工場と物流拠点にいる150名ほどはDigiFaceAIを使った顔認証による打刻を行っています。工場では各フロアにタブレットを配置し、タブレットのカメラを利用して顔認証を実施しています。「以前からタイムカードの打刻装置は各フロアに設置しており、同じ動線で顔認証での打刻が実施できるようにしています」と小松原氏は説明します。外部のシステムである人事・給与システムとの連携は、DigiSheet側で外部取り込み用にCSVを加工して抽出できるような形となっています。
DigiSheetおよびDigiFaceAI導入によって現場のDXを推し進めたことで、工場内の総務担当や各部署の上長が行っていた勤怠情報の収集や集計といった管理工数が大幅に削減できたと高く評価します。「各部署の所属長が行っていた毎月1時間ほどの事務作業が3分ほどで済んでいますし、全従業員の情報を集約する手間も大きく削減できました。工場内の各部署でのチェックが済めば、本社の人事部がそのままチェックに入るため、作業はゼロになっています」と実際使用している工場側の管理部も太鼓判を押しています。また、タイムカードなど毎月400枚ほどが必要だった各種紙をデジタル化することで削減できるなど、年間でも数千枚規模の紙削減につながっていると評価します。
外部機関の認証監査などの際も、労働時間の確認がその場でできるため、以前のように段ボールに保管された紙の書類を探すような手間がなくなるなど、デジタル化したことでのメリットは大きいと小松原氏は言及します。「以前のようにアナログな運用だった時は、出勤状況を電話で確認するといったこともありましたが、今は打刻された情報がリアルタイムで把握できるようになっています」。
DigiSheetの使い勝手については、直感的に操作できる部分が多く、マニュアルなどを熟読せずとも管理できる点が評価されています。同社独自で行っている複数人にまたがる承認フローも柔軟なカスタマイズによって実現しており、現場の運用をうまくシステムで吸収することに成功しています。
DigiFaceAIについては、工場でのテスト稼働時にきめ細かなチューニングを実施し、認識精度を高めていったことで大きなトラブルもなく運用できています。「元々精度の高さは実感していましたが、テスト時に認識しづらいメンバーが出てきたときには、必要に応じて閾値を調整いただくなどレスポンスよく対応いただけました。人数が多いわけではありませんが、1人でも不満があってはいけない部分です。ものづくりの現場だけにシステムにも高い精度が求められますが、それに近づけていただくことができて満足しています」と現場から評価の声が寄せられています。
紙の運用からデジタル技術を駆使した打刻の仕組みに大きく運用が様変わりしたものの、同社の仕様に適した形にカスタマイズを実施し、求める精度を達成するべくチューニング作業をしっかり行うなど、ヒューアップテクノロジーの支援体制も高く評価しています。「導入タイミングがコロナ禍だったこともあってテスト期間も長くなってしまった部分もありますが、手厚く支援いただけたことに感謝しています」と小松原氏は語ります。
労働時間管理の徹底に向けた早期の注意喚起や
セキュリティニーズへの対応に期待
現在は、出退勤の打刻時間の収集から勤怠情報の集計を行う基盤として活用していますが、今後については36協定をはじめとした労働時間の管理徹底に向けて、時間超過などのアラートを管理者に知らせる残業警告オプションなどを活用し、法規対応に向けた環境整備をさらに推し進めていきたい考えです。「時間管理は人事部側で当然把握していますが、早い段階で注意喚起していけるような形にしていきたい」と今後について小松原氏に語っていただきました。
- この事例で使われているサービスを見る